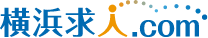梅雨の由来と梅干しの豆知識
いよいよ梅雨の季節がやってきましたね。日照時間が少なく、湿気も多いこの時期は、気分が沈みがちになる方も多いのではないでしょうか。
実は私も、じめじめした空気がちょっと苦手でして…ふと「どうして“梅”雨って書くんだろう?」という疑問が湧いてきました(笑)。
今回はそんな素朴な疑問をきっかけに、【梅雨】と【梅干し】をテーマに、ちょっとためになる豆知識をお届けします!
「梅雨」ってなぜ“梅の雨”?
梅雨という漢字は、もともと中国・長江流域の風習に由来します。日本と同じ頃に雨期を迎えるこの地域では、ちょうどその時期に梅の実が熟すため、「梅」の文字が使われるようになったと言われています。
ちなみに「つゆ」という読み方には諸説あり、以下のような語源が考えられています。
- 露(つゆ)説:雨で木々や草花に露がつくから
- 潰ゆ(ついゆ)説:熟した梅の実が潰れる「潰ゆ」から転じた
どちらにしても、やっぱり「梅」が深く関係しているんですね!
実は、梅はこの「梅雨」のある地域でしか育たない植物だそうですよ。
梅雨の不調に「梅干し」が効く!
梅雨の時期は、湿気のせいで体が重かったり、なんとなく不調を感じやすくなったりしますよね。そんな時におすすめしたいのが、日本の伝統食品「梅干し」です。
梅干しには次のような嬉しい効果があります。
- クエン酸による疲労回復効果
- 肩こり・筋肉痛の予防改善
- 塩分による利尿作用と、酸味による食欲増進
- 高い殺菌・防腐作用(お弁当の傷み防止にも◎)
特にクエン酸には、疲労を軽減し、細菌の繁殖を防ぐ力もあるため、梅雨時期にぴったりなんですね!
ただし最近は減塩タイプの梅干しが多く、防腐・殺菌効果が弱まっていることもあるので、お弁当に使う際は注意しましょう。
実は“種”の中身も食べられる!?
おまけ情報ですが、梅干しの種の中にある「仁(じん)」も食べられるんです!
(※ただし、未熟な青梅は有毒なので絶対に食べないように!)
まとめ|梅干しを食べて、梅雨を元気に乗り切ろう!
憂鬱になりがちな梅雨の季節ですが、梅干し1日1粒の習慣で、体の中から元気を取り戻せるかもしれません。
横浜市・金沢区で派遣や正社員として働く皆さん、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期。食生活からしっかり整えて、元気に働いていきましょう!